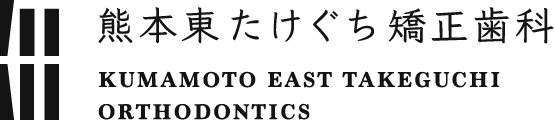小児歯科は、人が成人するまでの期間、歯と口腔の健康と機能を守るために保健指導や診療を行う歯科の領域です。小児期は胎生期、新生児期、乳児期、幼児期学童期、思春期から青年期までの十代全域を含む心身の成長、発達期にあたります。
小児期は、萌出歯(生えている歯)の状態によって、
無歯期、乳歯列期、混合歯列期と永久歯列期に分けられますが、智歯(第三大臼歯:親知らず)の生える頃までが小児歯科の対象年齢となります。小児歯科には以下のような特徴があります。
1. 小児の発達
小児は心身ともに成長、発達しており、生理的にも、知的、精神的にも常に変化していることをよく理解して、対応や指導、治療にあたる必要があります。また、小児歯科で行う歯科保健指導と診療には、患児本人が対象になるだけでなく親、保護者、家族をはじめ、保育土、教員など保育と教育、保健に関わる人も含めて対応することが必要になります。
「息をする」、「食べる」、「しゃべる」、「笑う(スマイル)」という口腔の機能は小児期に発達します。
2.小児期の歯科疾患
小児期には歯も身体の成長にあわせて、歯胚形成、乳歯の萌出から脱落、永久歯萌出から永久歯列へと変化するなど、一生の口腔機能の続をつくるきわめて大切な時期ですが、一方ではさまざまな問題が生じやすいのも特徴です。これらの問題に対して、小児歯科では対象児の年齢、発達段階、症状や予後などの点から総合的に判断して、専門的な対応がなされます。指導や治療が小児歯科だけで対応できないときには、歯科矯正や口腔外科などに紹介したり、保存的な歯冠修復、歯内療法や歯周病の治療、補綴治療については成人期の治療に委ねたりすることもあります。
3.小児のう蝕と歯周病
小児のう蝕と歯周病には、成人とは異なる特徴があるため、年齢や歯列の状態、症状にあわせて歯科保健指導、歯科予防処置と治療が行われます。
歯科保健指導は歯科診療所だけでなく、行政機関や保育所、幼稚園、学校、病院、療育施設など、小児の日常生活の場でも行われます。小児の歯科治療の多くは、一般歯科医院で行われていますが、小児患者だけを診療している小児歯科医院もあります。
小児歯科では、歯と顎・口腔の外傷の予防と治療、歯列不正(歯並び)や不正咬合(かみあわせの問題)があ
るときには、口腔習癖への対応、咬合誘導や歯列矯正も行われます。
4.小児の歯科治療
小児歯科では、歯を削ったり抜いたりするときの恐怖と痛みのコントロールがきわめて大切です。小児期に歯科で痛い治療や恐怖を経験すると、その後、歯科受診から遠ざかってしまったり、歯科恐怖症になったりするなど、大きな問題を残すことになりかねません。そのため小児歯科では安全、確実に治療が行えるよう Tell-Show-Do法をはじめとして、さまざまな行動管理(行動調整)の考え方、技法が応用されます。小児歯科では、乳歯と幼若な永久歯の健康管理と治療を最も重視しています。乳歯と幼若永久歯の治療では、歯の解剖学的特徴、歯冠と歯根の形成と吸収の状態、歯列と咬合の状態など、成人期とは異なる点が多いことから、より丁寧に診察、診査を行い、また、歯科衛生士も加わって、充分に信頼関係を築きながら治療を行うことが大切です。
~初めての方へ~
まずは『無料矯正相談』へ
矯正治療は、歯科治療の中でも専門性の高い分野です。
一生に一度の治療ですので、矯正歯科専門医院にご相談ください。
無料矯正相談では、患者さんが一番気になっている部分の確認や治療法の説明、費用についてなど十分な時間を設けております。
歯並びの影響により、顎の成長や健康寿命、人生観まで変わることがあります。
そのため患者さんの「人生の分岐点」という意識で臨んでいます。