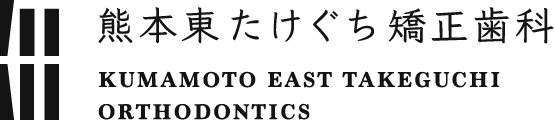歯科受診の時期と内容
小児が自分の意思で歯科を受診することはありません。このため、保護者の口腔健康管理に対する意識レベルが口腔健康管理への参加時期を決めることになります。
一般的には、1歳6か月児歯科健康診査で初めて歯科保健指導を受けることが多いです。しかし、母子健康手帳には6〜7ヶ月次の項目で、口腔の疾患や異常の有無が記載されています。また9〜10か月児の項目には、歯の萌出時期や萌出状態、歯の形や色、口腔の疾患や異常についての質問事項があります。いずれも、小児科医による成長発育のための健康診査でありますが、「歯科診療所を受診するように」という項目も含まれています。1歳児の健康診査で、初めて歯の状態を記載する項目があります。基本的には仕返しによる、歯の萌出状態の診査を受けることになっていますが、歯科診療所を受診する保護者は多くはありません。
(1)乳児期
無歯期(生後6か月くらいまで)に歯磨きは必要ないが、哺乳により口腔粘膜や舌表面に汚れが付着するため、綿棒やガーゼなどで清拭します。この時期から口腔内に触れられることに慣れさせることや、大人が小児の前で楽しそうに歯磨きをするのを見せることにより、小児に歯磨きの習慣をつけて、本格的な口腔清掃へ移行することができるため、歯磨きは楽しく気持ちの良いものであるという感覚を身につけさせる必要があります。乳歯萌出開始後は歯ブラシが触れる感覚に慣れさせながら、口腔清掃を習慣化させていきます。
哺乳の開始により、食生活のリズムが形成される時期でもあります。食べる楽しさを体験し、食を通じた周りの人とのコミュニケーションは、小児の成長、発達へとつながります。
ミュータンスレンサ球菌は親から子に伝播します。口腔内のミュータンスレンサ球菌を減らすために、保護者はブラッシングする習慣を身につけ口腔内環境を整えるとともに、う蝕の治療をして、口腔内にう蝕病巣をもたないよう、保護者に指導します。
(2)幼児期前期
幼児期前期は乳臼歯が萌出し、う蝕が発生しやすい時期となるため、う蝕予防の積極的な口腔健康管理が必要になります。
離乳が完了し、生活習慣を形成する時期であるため、口腔清掃だけでなく、生活のリズムやバランスの良い食生活などについての保健指導も大切です。1日3回の食事と、1日1〜2回の間食を規則正しくとる習慣をつける必要があります。間食はスクロースを含まないものを、3度の食事に影響しない程度の量を与えるよう指導します。さらに、離乳完了後の哺乳ビンの使用や甘味飲料の頻回摂取にも注意を与える必要があります。乳前歯う蝕の好発時期であるため、仕上げ磨きの状況を確認します。萌出直後の歯は最もう蝕感受性が高いだけでなく、フッ素が作用する効果も大きいです。定期的に歯の検査とフッ化物歯面塗布を受け、う蝕の早期発見に努めるように指導する必要があります。
(3)赤ちゃん専門外来
小児の口腔の健康を早期から管理していくことを目的として、生後3~4ヶ月頃から歯科受診できる施設を設置している病院があります。歯科と産婦人科が併設されており、妊産婦だけではなく、生まれてくる子の口腔健康管理を支援しています。健全な口腔機能を一生維持して行くためには、妊産婦へのアプローチが、その基本となるのです。
~初めての方へ~
まずは『無料矯正相談』へ
矯正治療は、歯科治療の中でも専門性の高い分野です。
一生に一度の治療ですので、矯正歯科専門医院にご相談ください。
無料矯正相談では、患者さんが一番気になっている部分の確認や治療法の説明、費用についてなど十分な時間を設けております。
歯並びの影響により、顎の成長や健康寿命、人生観まで変わることがあります。
そのため患者さんの「人生の分岐点」という意識で臨んでいます。